今日(7日の朝)はさすがに「おちつけ」モードですが、昨日はいわゆる高市トレード、サナエノミクスなどの期待で日経平均が大幅に上昇しました。円安による物価高をどうするのかはいまのところまだ政策が見えていませんが、やはり株式市場の上昇は重要です。とりあえず市場は好意的に、そしてものすごい期待感で受け入れたということでしょう。一安心です。こういう話を「私には関係ない」とする人たちもいますが、金融という流れからスタンドアローンでいられる人などいません。私も日本100%の投資などを増やして、微弱ながらも加わりたいと思っています。
・・と、金融ブログみたいな始まり方でしたが、本題はノーベル賞関連です。もう大きく報じられていますが、坂口志文教授(など3人)がノーベル医学生理学賞を受賞しました。おめでとうございます。医学生理学受賞だけで6人目です。このシーズンになると韓国メディアはいつもノーベル賞ノーベル賞(科学部門)と多くの記事が出しますが、でもそういう記事の多くは(全てではありませんが)まだ「普通」です。日本側の受賞を凄いとちゃんと書いているからです。今回もそうですが、ソウル経済(6日)の記事で特に印象的なのは、「戦後わずか9年で湯川秀樹がノーベル物理学賞を受賞した」とし、その力は明治時代から(明治維新から)81年間、積み上げてきた科学分野での力があったからだ、としています。
昔にそういうのがあった、というだけではないでしょう。それがちゃんと受け継がれてきて、努力が重なって、いまの「強国」があるわけです。他にも、多くの専門家が「積み上げてきたものが違いすぎる」という指摘をしています。韓国では、実は日本は「◯◯大国(強国)」という話をすると、話の流れがすごく気まずくなったりします。たとえば、これはリアル体験でもありますが、「韓国では、金融大国としての日本の姿はほとんど知られていない」というテーマになると、結局は「そんなはずない」という結論になったりします。今回もファイナンシャル・ニュース(7日)が「実は日本は免疫学強国」という記事を載せていますが、あまり反応もないし、なにより、そんな話題の記事が載るのも、ノーベル賞を受賞した時だけです。中身も、ほとんど日経新聞の記事のままですし。こういう反応が、「韓国メディアのノーベル賞関連記事は『面白い(意味深)』」とされる所以かもしれません。以下、両紙の記事を<<~>>で引用してみます。
<<・・坂口志文日本大阪大学名誉教授が6日(現地時間)、米国生物学者のメアリー・ブランコウ、フレッド・ラムズデルと共に今年ノーベル賞生理医学賞の受賞者に選ばれた。これにより、日本の生理医学賞受賞者は6人に増えた・・・・NHKによると、日本人のノーベル賞受賞は、1949年の湯川秀樹博士が物理学賞を受賞してから、今回まで30回目を迎えた。1901年のノーベル賞受賞以来、日本出身の受賞者としては外国国籍取得者も含め、個人で29人、団体1箇所と集計された。分野別に見ると、これまで物理学賞は12人、化学賞8人、生理医学賞5人、文学賞は2人がそれぞれ受賞した。
日本人初のノーベル賞受賞者である湯川博士は、戦後から4年しか経っていないの1949年に物理学賞を受けた。彼は1868年明治維新で日本が西洋科学を本格的に受け入れた後、81年間積み上げてきた科学研究が土台になって受賞につながったという評価を受けた。物理学、化学、生理医学など自然科学分野の受賞は、眞鍋淑郎博士に続いて4年ぶりだ・・・・坂口教授は「すばらしい栄光」とし「癌も治せる時代が必ず来る」と明らかにした。ノーベル賞委員会は今回の受賞に対して「末梢免疫寛容に関するこれらの画期的な発見で人間の免疫システムがどのように機能するのか、そしてなぜ私たち全員が深刻な自己免疫疾患を患うのか、その理解を高める上で決定的役割を果たした」と説明した。
一方、時代別に見ると、経済が高度成長を重ねた中で基礎科学投資が実を結んだことで、2000年以降日本人受賞者が急増したという分析が出ている。2000~2002年には3年連続で化学賞を受け、2002年には化学賞と物理学賞同時受賞で同年初めて日本人二人がノーベル賞受賞者名簿に名前をあげた。 2008年には物理学賞同時受賞を含めて、年4人の日本人受賞者が誕生した(ソウル経済)・・>>
<<・・日本は、免疫研究で伝統的に強い。岸本忠三 大阪大教授が発見した「インターロイキン6(IL-6)」は、自己免疫疾患の一種であるリウマチ関節炎治療剤「アクテムラ(Actemra)」の開発につながった。2018年にノーベル生理医学賞を受賞した本庶佑 教授が発見した「PD-1」分子は、がん免疫治療剤「Opdivo」と「キトルダ(Keytruda)」開発の基盤となった。このように日本では産学協力による免疫研究と新薬開発の成功事例が相次いでいる。このような流れで、坂口教授の研究も日本で長年続いてきた免疫学研究の伝統の結果ともいえる、と日経新聞は伝えた・・
・・坂口教授は前日の日経とのインタビューで「(近代医学の父と呼ばれる)北里柴三郎博士以来、日本には免疫学の伝統が続いてきた。学問の伝統は非常に重要だ」とし、日本免疫学の強みについて言及した・・・・「伝統の免疫学強国」日本だが、坂口教授は、政府の研究支援を今より拡大しなければならないと強調した。彼は「(日本の研究支援は)米国や中国に比べて資金が少ない。名目国内総生産(GDP)が似たドイツと比較しても、免疫研究資金は3分の1水準に過ぎない」と指摘した。続いて「若い研究者が研究に専念できる環境と財政的支援を維持することが重要だ」と強調した(ファイナンシャルニュース)・・>> 今日の更新は、これだけです。次の更新は明日(8日)の11時頃になります。
ここからはいつもの告知ですが、新刊のご紹介です。いつも、ありがとうございます。今回は、<韓国リベラルの暴走>という、李在明政権関連の本です。新政権での日韓関係について、私が思っていること、彼がいつもつけている国旗バッジの意味、韓国にとっての左派という存在、などなどを、自分自身に率直に書きました。リンクなどは以下のお知らせにございます。

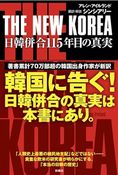 ・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年8月30日)<韓国リベラルの暴走>です。韓国新政権のこと、日韓関係のこと、韓国において左派という存在について、などなどに関する本です。・準新刊は<THE NEW KOREA>(2025年3月2日)です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。・既刊、<自民党と韓国>なども発売中です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。
・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年8月30日)<韓国リベラルの暴走>です。韓国新政権のこと、日韓関係のこと、韓国において左派という存在について、などなどに関する本です。・準新刊は<THE NEW KOREA>(2025年3月2日)です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。・既刊、<自民党と韓国>なども発売中です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。