日本がまたノーベル賞を受賞しました。もうびっくりです。金属有機構造体・・これを聞いて「アニメに出てくる言葉かな」と思ってしまって恐縮ですが・・で北川進 京都大特別教授(他にリチャード・ロブソン オーストラリア メルボルン大教授、オマー・ヤギー 米国 カリフォルニア大バークリー校教授が共同受賞)がノーベル化学賞を受賞しました。おめでとうございます。二日前にも同じテーマで書いたような気もしますが、多くの韓国メディアも記事を出しています。ただ、二日前に比べるとちょっと勢い(?)が弱くなった気はします。ネットでは(単に羨ましいというコメントも無数にありますが)「戦時に人間相手に良からぬ実験をしたから」という意見が目立っています。そういえば、この前中国でそんな映画が公開されたりしました。こういうところは確実に「価値観を共有」しているのでしょう。
そんな中、「半分は羨ましく、半分は懸念される」という記事があったので、ちょっとチョイスしてみました。京郷新聞(9日)です。羨ましいのはわかるけど、懸念ってなんのことかなと思って読んでみたら、「韓国が基礎科学に投資するようになったのは2010年あたりだから、(日本の事例を見て)少なくともあと十数年は受賞者が出ないという意味ではないか」だから懸念される、という意味でした。どこからどこまでを見るのかで変わるとは思いますが、日本の基礎科学投資がそんなに短い期間(記事で言うには約30年)だけのものとは思えません。二日前に紹介した記事では、「明治維新から」としていました。実際、戦後すぐにノーベル賞を受賞したケースもありますし。
また、先のオマー・ヤギー教授といっしょに研究をしたこともある韓国の科学者は、「韓国の場合、(積極的に科学分野に投資するといっても)ナノ・テクノロジーになったり、グリーン(エコ)になったり、AIになったりなど、10年で「入れ替わる」とのことでして。京郷新聞にも載っていますが、中央日報(9日)のほうがわかりやすく書いてあります。また、他の国はどうなのかわかりませんが、韓国は憲法で「国が科学発展を振興させる理由は、国内の経済発展のため」と刻まれている、とのことでして。まずこれを変えるべきではないのか、という話も出てきます。以下、<<~>>で引用してみます。
<<・・日本が、今年のノーベル生理医学賞と化学賞で、同時に受賞者を輩出しながら、韓国では「私たちにはいつごろこんな慶事を迎えることができるのか」という、半分は羨ましく、半分は懸念されるという声が広がっている。韓国の科学界では、新進研究者が失敗の可能性を心配せずに研究を続けることができる風土を造成し、科学技術政策目標を「自国経済発展」から「人類の問題解決」に拡大しなければならないという声が出ている。国内科学界では、日本が頻繁に科学部門ノーベル賞を受けることができるなによりの理由として、基礎科学に対する着実な投資を挙げている。今年まで日本の科学部門ノーベル賞受賞者は計27人(物理学賞12人、化学賞9人、生理医学賞6人)だ。このうち70%(19人)が2001年以降に賞を受賞した。
韓国研究財団が2021年に出した資料である「ノーベル科学上の核心研究と受賞年齢」を見ると、ノーベル賞受賞者たちは研究の着手から受賞まで、平均で31.8年がかかった。日本が1970年代以降、政府レベルで積極的な基礎科学投資をした成果が、21世紀に入って爆発的に現れているという話だ。韓国の状況は日本と違う。政府レベルで積極的な基礎科学投資が行われたのは2010年代以降だ。単純計算すれば、韓国が科学部門ノーベル賞の有力候補国になる日は、今から十数年後になるという話だ。問題は、基礎科学投資の方向が、未来のノーベル賞受賞者を輩出するのに適しているかについて懸念が出ているという点だ。
北川教授と共に今年のノーベル化学賞共同受賞者に選ばれたオマーヤギー米国カリフォルニア大学バークレー校教授と共同研究を行ったことがある、キム・ジャホン崇実大化学科教授は、「(ノーベル賞を受けるには)新進研究者たちが創造的で挑戦的な研究をしなければならない」と「しかしそんな研究は失敗の可能性が高いので、(国内では)研究費を受け取るのが難しい」とした。数年ぶりに短期成果を出すことが重要な国内風土において、長い呼吸で結果を待ってくれと要求することは、容易ではないということだ。
韓国科学技術政策目標を「自国経済振興」から「人類課題解決」に拡大しなければならないという声も出ている。一例として、憲法第127条は、国家が科学技術を振興しなければならない理由を、国民経済発展だと釘付けしている(京郷新聞)・・>>
インタビューの部分、中央日報はこう書いています。「ヤギー教授とMOF(※金属有機構造体、Metal Organic Framework)を共同研究した経験があるキム・ジャホン崇実大化学科教授は、日本の相次ぐノーベル賞受賞に対して『失敗を甘受して基礎科学に着実に投資した結果』と評価した。彼は『韓国は研究費が時流によって、ナノ、グリーン技術、AIなどなどと、10年周期で変わったりするので、研究者たちが一つのテーマを持続することが難しい』と付け加えた」。そういえば、尹錫喜政権で科学関連の予算が大幅に削減されたという話もありましたが、「韓国版エヌビディアを育てる(続報なし)」としている李在明政権では、どうなのでしょうか。
ここからはいつもの告知ですが、新刊のご紹介です。いつも、ありがとうございます。今回は、<韓国リベラルの暴走>という、李在明政権関連の本です。新政権での日韓関係について、私が思っていること、彼がいつもつけている国旗バッジの意味、韓国にとっての左派という存在、などなどを、自分自身に率直に書きました。リンクなどは以下のお知らせにございます。

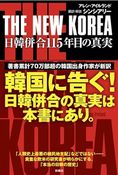 ・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年8月30日)<韓国リベラルの暴走>です。韓国新政権のこと、日韓関係のこと、韓国において左派という存在について、などなどに関する本です。・準新刊は<THE NEW KOREA>(2025年3月2日)です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。・既刊、<自民党と韓国>なども発売中です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。
・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年8月30日)<韓国リベラルの暴走>です。韓国新政権のこと、日韓関係のこと、韓国において左派という存在について、などなどに関する本です。・準新刊は<THE NEW KOREA>(2025年3月2日)です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。・既刊、<自民党と韓国>なども発売中です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。