超短時間就業者と非自発的失業者についての記事があったので、チョイスしてみました。昨日のライダーもそうでしたが、すべて、不況を表すものでありましょう。今日(6日)のマネートゥデイです。まず非自発的失業ですが、検索して出てきた京都府の「よくある質問」ページに、「人員整理・事業不振・定年等で前の仕事をやめたために仕事を探し始めた者のことをいい、一方、自発的な離職による失業者とは、自分又は家族の都合で前の仕事をやめたために仕事を探し始めた者のことをいいます」と、わかりやすい解説がありました。日本の統計局労働力調査などでは「非自発的離職」となっています。超短時間就業者とは、これは公式用語なのかそれとも一般的に使う用語なのかはわかりませんが、1週間に1時間~17時間働く人たちのことです。
人それぞれ事情があるでしょうし、働く時間が短いから何もかも問題だと言うことはできないでしょうけど、経済関連では、一般的に「もっと働きたいけど、それができない」意味とされます。韓国の経済活動参加人口は約2800万人とされていますが、その中で超短時間就業者が250万人(2024年基準)で、これは2023年に比べて10%も増加した数値になります。非自発的失業は約137万人(2024年基準)でした。これもまた、2023年に比べると10%近く増加しています。非自発的失業については、日本のデータがちょうど手元にあったので合わせて紹介しますと、今年1月31日公開(2024年12月データ)の日本統計局労働力調査(※PDFファイルです)「完全失業者」カテゴリーにありますが、35万人でした(そのうち「勤め先や事業の都合」が18万人)。以下、<<~>>で引用してみます。
<<・・4日午後、(※経済メディア『マネートゥデイ』の)記者が訪れたソウル「建大・味の街」はとても静かだった。道路沿いの商店街1階のあちこちは廃業に伴う空室がずらりと並んでいた。イオクヒ氏が運営する食堂も、ただ静かだった。昨年11月末に食堂を開いたが、弾劾政局が重なり、2ヶ月連続で赤字を出した。職員を減らすしかない状況になってしまった。店主は「オープンするときには職員が6人もいたのに、今は4人に減った。以前は30人だった他の店は、今は9人だ。人が足りないと、週末にアルバイトを雇う」とし「材料費や人件費などが上がるから、新型コロナの時より今がもっと難しい」と話す。
建国大学校路で数十年間も焼肉屋を運営したアン某さん(70代)は、客のいない食堂内で奥さんと食事中だった。2023年には職員4~5人を雇うほど余裕があったが、今は夕方の時間帯だけ、キッチンとホール職員1人ずつだけを残しておいた。アン夫婦は「『売り上げ』とも言えない状況だ。売上が80%以上は減少した」とし「今は(職員を)3~4時間だけ働かせている。材料費は後回しにできるとしても、人件費は与えなければならないので、毎日のように借金をしている」と話した。東大門ファッションタウンも同じだった。同日、東大門区平和市場で財布を開くゲストは多くなかった。子供と共に色とりどりの帽子と手袋を見物する家族単位の外国人観光客が目立ったが、実際にものを買う人の姿は少なかった。
キム・ミン平和市場株式会社総務課課長は「(市場で)人件費を減らそうとする人が多い。市場1階に位置する大きな売り場でも、アルバイトの数を減らした」とし「大部分、親族関係者たちが一緒に営業している。ある程度広い店は全部家族でやっていると思っていい」と話した。専門家たちは、高い最低賃金などで人件費負担を感じている自営業者の現状が、非自発的失業者や超短時間就業者の増加につながると指摘している。経済的に難しい自営業者が職員を解雇したり、自ら店を畳んだりしたことで失業者が増え、そして、週休手当と退職金などを与えなくてもいい「超短期労働者」ばかり雇っているわけだ。
統計庁雇用動向マイクロデータによると、1週間に1~17時間だけ働く「初短時間就業者」は昨年250万人で、2023年の226万8000人に比べて10.2%増加した。関連統計が作成された1980年以来、最大規模を記録した。昨年、非自発的退職者は137万2954人だった。これは2023年と比較すると10万6761人、9%近く増えた数値だ。イ・ビョンフン中央大学社会学科名誉教授は「民生景気がずっと難しく、年末特需が欲しかった時期の12月3日に戒厳事態が起きて、消費心理がさらに低くなった」(マネートゥデイ)・・>>
韓国で言う「仕事割り(退職金や手当などの負担を減らすため、短い時間だけ働くようにする)」のことですが、尹大統領というより、文在寅政権から始まった「所得主導成長」政策の影響が大きいと見るべきではないでしょうか。いうまでもなく、専門家たちは「結局、システムそのものの質の問題になる」としています。引用部分にはありませんが、「政府が福祉政策でなんとかするしかないけど、そのためにはとんでもない金額が必要になる」とも。
ここからはいつもの告知ですが、久しぶりに新刊のご紹介です。本当にありがとうございます。新刊は自民党と韓国」という題です。岸田政権・尹政権になってから、「関係改善」という言葉がすべての議論の前提になりました。果たして、本当にそうなのでしょうか。いや、それでいいのでしょうか。じゃ、同じ路線でないのは、たとえばこれから日本政府の路線変更があった場合は、それは「改善」ではないのでしょうか。そんな疑問に対する考えを、自分なりに、自分に率直に書いてみました。リンクなどは以下のお知らせにございます。
本エントリーにコメントをされる方、またはコメントを読まれる方は、こちらのコメントページをご利用ください。以下、拙著のご紹介において『本の題の部分』はアマゾン・アソシエイトですので、ご注意ください。

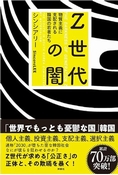 ・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2024年12月22日)<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。・準新刊(2024年5月2日)は、<Z世代の闇>です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。・既刊として、<韓国の絶望、日本の希望(扶桑社新書)>も発売中(2023年12月21日)です。「私たち」と「それ以外」、様々な形で出来上がった社会の壁に関する話で、特に合計出生率関連の話が多目になっています。・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。
・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2024年12月22日)<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。・準新刊(2024年5月2日)は、<Z世代の闇>です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。・既刊として、<韓国の絶望、日本の希望(扶桑社新書)>も発売中(2023年12月21日)です。「私たち」と「それ以外」、様々な形で出来上がった社会の壁に関する話で、特に合計出生率関連の話が多目になっています。・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。