「ゾンビ企業」。本ブログでも何度も取り上げた用語です。インタレストカバレッジレシオ、利子補償倍率が1にならない、すなわち「企業が稼いだ収益より、払うべき利子のほうが多い」企業のことです。機関、メディアによって定義はちょっと異なりますが、そんな状態がしばらく続くと、該当企業をゾンビ企業と言います。韓国だけでなく、世界的に結構話題になっていて、IMFなど複数の機関が定期的に報告書を出しています。ちなみに、IMFは「利子補償倍率が1未満であり、レバレッジ比率(総債務/総資産)が同種業界の中位値より高く、売上増加率がマイナスの状態が2年連続で続いた企業」としていますが、機関やメディアによって定義が少しずつ異なります。
で、その限界企業ですが、韓国経済人連合会という団体が、G5(日本、米国、イギリス、ドイツ、フランス)と韓国の上場企業を対象に、関連データを分析し、発表しました。日本ではあまり目にしない話題ですが、韓国では前から結構話題になっていたこともあり、今回も複数のメディアが記事を出しています。今回のソース記事「クッキーニュース」では「利子補償倍率1未満が3年続いた企業」を「限界企業」、1年だけの企業を「一時的限界企業」としています。どうやら、19.5%で2位(1位はアメリカ)だそうで、増加率も12.3%p、2016年7.2%から2024年7~9月期19.5%で、2位でした。こちらもアメリカ1位。日本関連データも出ています。以下、<<~>>で引用してみます。しかし、この件(だけでもありませんが)、本当に改善しませんね。
<<・・国内上場企業5社のうち1社は利子すら稼ぐことができない「限界企業」と判明した。上場企業においての限界企業の比重は、米国に次いで2番目に高い水準だ。韓国経済人協会(韓経協)が韓国とG5国家(米国・日本・ドイツ・イギリス・フランス)上場会社を分析した結果、昨年7~9月期基準で韓国の限界企業の割合は19.5%(2260社のうち440社)で米国(25%)に次いで2番目に高いと、6日明らかにした。続いて、フランス(19.4%)、ドイツ(18.7%)、イギリス(13.6%)、日本(4.0%)の順だった。限界企業とは、利子補償倍率(営業利益/利子費用)が3年連続1を下回る企業をいう。営業利益だけで利子費用を負担する余裕がない企業という意味だ。
韓経協は、限界企業が主要国に比べて急速に増加したのは、景気不振の長期化に伴う販売不振・在庫増加で企業の収益性が大きく下がったからだと分析した。国内業種別にみると、不動産業(33.3%)、専門・科学・技術サービス業(24.7%)、卸売・小売業(24.6%)、情報通信業(24.2%)などの順で限界企業の割合が高かった。限界企業の割合は2016年7.2%から2024年7~9月期の19.5%に、12.3%p増加した。韓国の限界企業の比重上昇幅は米国(15.8%p)に次いで2番目に大きく、英国(6.9%p)、フランス(5.4%p)、日本(2.3%p)、ドイツ(1.6%p)は10%pを超えなかった。
当該年度だけが利子補償倍率1未満の「一時的限界企業」比重も36.4%で、米国(37.3%)よりは低かったが、フランス(32.5%)、ドイツ(30.9%)、英国(22.0%)、日本(12.3%)より高かった。日本と比べると3倍近く差がある。イサンホ(韓経協)経済産業本部長は、「最近、国内企業は深い内需不振とトランプ2.0による輸出不確実性で、経営圧迫が大きく加重されている状況だ」とし「企業が直面した難関を克服し、将来のグローバル競争力を先取りできるように制度的支援を強化しなければならない」と話した(クッキーニュース)・・>>
ちなみに、去年5月、韓国銀行がIMFのレポート(2023年発表)を引用して、複数のメディアがそのレポートを記事にしました。2024年5月21日ニュース1などによると、IMFが2000年から2021年まで(平均値)64カ国の「ゾンビ企業」を分析した結果、韓国が7位(7番目に該当企業が多い)でした。 引用してそのまま終わりにしますが、明日は1日休みをいただきます。次の更新は2月9日の11時頃になります。
<<・・2年連続で、経営活動を通じて利子も返済できなかった企業の割合が、韓国には他の国より高かったという意味になる。IMF分析で韓国より限界企業の割合が高く現れた6カ国は、ヨルダン、キプロス、ギリシャ、クロアチア、ポルトガル、カナダなどだった。先進国の中で唯一カナダだけが韓国を上回った・・・・これにIMFは「オーストリア、フィンランド、スペイン、ドイツ、オランダ、フランスなどヨーロッパ諸国の上場企業は限界企業の割合が少ない傾向を示したが、カナダ、韓国、オーストラリアなど他の先進国の場合は限界企業の割合が高かった」と明らかにした・・・・IMFはこのような限界企業を「ゾンビ企業(zombie firms)」と呼び、「グローバル金融危機と新型コロナ拡散以後、このような企業が世界的に増える現象が観察されてきた」と付け加えた(ニュース1)・・>>
ここからはいつもの告知ですが、久しぶりに新刊のご紹介です。本当にありがとうございます。新刊は自民党と韓国」という題です。岸田政権・尹政権になってから、「関係改善」という言葉がすべての議論の前提になりました。果たして、本当にそうなのでしょうか。いや、それでいいのでしょうか。じゃ、同じ路線でないのは、たとえばこれから日本政府の路線変更があった場合は、それは「改善」ではないのでしょうか。そんな疑問に対する考えを、自分なりに、自分に率直に書いてみました。リンクなどは以下のお知らせにございます。
本エントリーにコメントをされる方、またはコメントを読まれる方は、こちらのコメントページをご利用ください。以下、拙著のご紹介において『本の題の部分』はアマゾン・アソシエイトですので、ご注意ください。

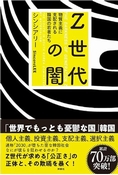 ・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2024年12月22日)<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。・準新刊(2024年5月2日)は、<Z世代の闇>です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。・既刊として、<韓国の絶望、日本の希望(扶桑社新書)>も発売中(2023年12月21日)です。「私たち」と「それ以外」、様々な形で出来上がった社会の壁に関する話で、特に合計出生率関連の話が多目になっています。・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。
・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2024年12月22日)<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。・準新刊(2024年5月2日)は、<Z世代の闇>です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。・既刊として、<韓国の絶望、日本の希望(扶桑社新書)>も発売中(2023年12月21日)です。「私たち」と「それ以外」、様々な形で出来上がった社会の壁に関する話で、特に合計出生率関連の話が多目になっています。・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。