ミュンヘン安保会議で、日米韓外相会談が行われました。米韓外相会談もあったので、いつもより韓国メディアの関連記事が目立っています。注目されるのはやはり関税関連ですが、具体的なことまで議論する時間はなかったでしょう。ただ、今回の日米韓外相会談の共同声明で、一部メディアが台湾関連内容に注目しています。まず、日経新聞の「日米首脳会談 共同声明全文」を見てみると、「国際機関への台湾の意味ある参加への支持」という内容がありました。これはEU側からも同じ内容のフレーズが出ています。今回の日米韓外相会談でもこの件が議題になり、同じ表現が入る予定だった、とのことですが・・
・・なぜか、こうなりました。「They also expressed support for Taiwan’s meaningful participation in appropriate international organizations(台湾の適切な国際機関へ有意味に参加することを支持する)」。適切ってどういうことでしょうか。適切なのかどうかは誰が決めるのでしょうか。各記事を読んでみると、パッと見ると問題無さそうでも、「有意味な参加」をかなり曖昧にしてしまいます。韓国日報など複数のメディアによると、これは韓国側が要請したものであり、韓国側は「中国への配慮による表現だ。中国側もきっと私たちの配慮を認識しているだろうと期待している」と話しました。以下、<<~>>で引用してみます。
<<・・「彼らはまた、台湾の適切な国際機関に有意義な参加を支持することを表明した」・・・・ジョテヨル外交部長官(※外相)が、ドイツ・バイエルン州(ミュンヘン)で開かれたミュンヘン安保会議をきっかけに15日(現地時間)、マルコ・ルビオ米国国務部長官、岩屋毅日本外務大臣と日米韓外交長官会談を行った後、導出された共同声明には、このような文句がある。三国がこのような内容に合意したのは今回が初めてだ。これをめぐって、台湾問題に関する韓国政府の既存原則である「一つの中国政策」と合わないのではないか、という解釈が出た。「台湾の国際機関加入支持」という表現は「台湾の国家性を認める」という意味と解釈できるからだ・・
・・外交部は既存の原則と変わらないと説明した。「適切な(appropriate)」という言葉があるためだ。「国際機関」を「適切な」という単語に修飾することで、「国家性を認めない国際機関」などと解釈する余地が生じたということだ。15日、ミュンヘンで会った外交部関係者はこのように説明しながら、「台湾の世界保健総会(WHA)参観局(オブザーバー)資格参加」をその事例とした・・・・外交部によると、「適切な」という言葉は、韓国が追加するように要請したものだ。最近、日米首脳は会談後の声明を通じて「台湾の国際機構加入支持」に合意し、これを日米韓外交長官会談でもそのまま続けようとしたが、韓国がこれをそのまま受け入れなかったということだ。これは、米国の対中圧迫に参加することで米国から得られるものを得ながらも、中国をできるだけ刺激しないためだという意図だと解決される。
ただし、中国の反発の可能性もある。中国をインド・太平洋地域のリスクと規定するドナルド・トランプ2期米国行政府の「圧迫」に韓国が足並みを揃えるとみられるからだ。米国国務省がホームページに掲示された「台湾との関係に関するファクトシート」資料を更新し、台湾独立を支持しないという部分を削除したのも、意味がある。外交部高位当局者は16日、「日米韓会談の調整過程で『適切な』という表現を入れたのは、われわれがそれなりに(中国を)配慮しながら努力した結果であるだけに、中国がこの部分を十分に認識しているだろうと期待する」と明らかにした。一方、ジョテヨル長官はトランプ2期行政府の発足以来初めて、マルコ・ルビオ米国国務部長官と15日会談したことに対し、16日米韓同盟の強化、対北朝鮮協力、日米韓協力拡大に対する韓米の一致した方向性を再確認した(韓国日報)・・>>
引用部分最後の行にも、見てみると中国関連の話はでていません。やはりこういう部分は、政権が変わっても、大統領がいてもいなくても、変わっていません。最後にテレ朝ニュースからの引用ですが、日米首脳会談のあと、台湾の頼総統はSNSに「支持に深く感謝」と書きました。 <<・・トランプ大統領と石破総理による8日の日米首脳会談を受けて、台湾の頼清徳総統は自身のSNSに「(両首脳が)台湾海峡の平和と、台湾の国際参加を強く支持してくれたことに深く感謝します」とのコメントを載せました。日米首脳の共同声明では台湾海峡の平和と安定の重要性が強調され、力による一方的な現状変更への反対を表明しています(テレ朝news)・・>>
ここからはいつもの告知ですが、新刊のご紹介です。本当にありがとうございます。自民党と韓国」という題です。岸田政権・尹政権になってから、「関係改善」という言葉がすべての議論の前提になりました。果たして、本当にそうなのでしょうか。いや、それでいいのでしょうか。じゃ、同じ路線でないのは、たとえばこれから日本政府の路線変更があった場合は、それは「改善」ではないのでしょうか。そんな疑問に対する考えを、自分なりに、自分に率直に書いてみました。リンクなどは以下のお知らせにございます。
本エントリーにコメントをされる方、またはコメントを読まれる方は、こちらのコメントページをご利用ください。以下、拙著のご紹介において『本の題の部分』はアマゾン・アソシエイトですので、ご注意ください。

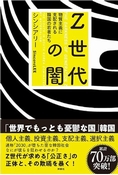 ・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2024年12月22日)<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。・準新刊(2024年5月2日)は、<Z世代の闇>です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。・既刊として、<韓国の絶望、日本の希望(扶桑社新書)>も発売中(2023年12月21日)です。「私たち」と「それ以外」、様々な形で出来上がった社会の壁に関する話で、特に合計出生率関連の話が多目になっています。・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。
・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2024年12月22日)<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。・準新刊(2024年5月2日)は、<Z世代の闇>です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。・既刊として、<韓国の絶望、日本の希望(扶桑社新書)>も発売中(2023年12月21日)です。「私たち」と「それ以外」、様々な形で出来上がった社会の壁に関する話で、特に合計出生率関連の話が多目になっています。・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。