たまにはポジティブなニュース(当社比)でもどうぞ。昨日の夜、石破茂総理がドナルド・トランプ米国大統領と電話会談しました(NHK)。詳しくなにを話したのかまではわかりませんが、「ああなんということだ、これでは日本企業が米国に投資できる余力がへってしまうではないか」という趣旨を話したようです。ソウル新聞などのメディアが報じていますので後で引用しますが、米国側の反応は意外としっかりしており、日本を優先協議対象に指定、迅速に担当(ベッセント財務長官など)まで決まりました。ロイターなどによると、トランプ大統領は記者団に「米国は日本と素晴らしい関係を築いている。今後もこの関係を維持していく」と話した、とも。いつもながら言ってることとやってることが一致してない気もしますが。
また、日本製鉄のUSスチール買収計画について、トランプ大統領が対米外国投資委員会(CFIUS)に再審査を命ずる文書に署名した、というニュースもありました(日テレNEWSなど)。時系列がちょっと気になるところですが、株探(かぶたん)によると、どうやら電話会談のあとのようです。指示出したのが電話会談の前なのか、それとも前から決まっていたことで、たまたま署名が電話会談のあとになったのかまではわかりませんが。日本、米国の株式市場も、多少ではあるものの下げ止まりラインを意識するようになったように見えます(あくまで個人的な見方です)。少しでも良い方向に進んでくれると嬉しいのですが。以下、<<~>>で引用してみます。
<<・・石破総理大臣は7日夜、アメリカのトランプ大統領とおよそ25分間、電話会談を行いました・・・・石破総理大臣は「日本が5年連続で世界最大の対米投資国である中、アメリカの関税措置により、日本企業の投資余力が減退することを強く懸念している」と述べました。その上で、一方的な関税ではなく、投資の拡大を含めた日米双方の利益になる幅広い協力のあり方を追求すべきだとして措置の見直しを求めました。そして、両首脳は今後も率直で建設的に協議するため、7日のやり取りを踏まえ、双方で担当閣僚を指名し、協議を続けていくことで一致しました・・
・・電話会談のあと石破総理大臣は記者団に対し、「トランプ大統領からは国際経済においてアメリカが現在置かれている状況について率直な認識が示された。わが国としては協議を通じてアメリカに対し措置の見直しを強く求めていく」と述べました(NHK、記事の時点ではまで「協議のための日米の担当者が誰になるかはまだ名前があがっているわけではない」のなっていますが、このあと、米国ではベッセント長官が担当となりました)・・>>
<<・・トランプ大統領は7日、日本製鉄によるUSスチールの買収提案について「さらなる措置が適切かどうか判断する」として改めて審査を行うようCFIUS=対米外国投資委員会に指示しました。CFIUSは、USスチールの買収提案に安全保障上の懸念がないか改めて審査し、45日以内に報告書を提出します・・・・トランプ大統領の指示で審査が見直されることで、買収阻止の決定が覆る可能性が出てきました。USスチールは7日、トランプ大統領が日本製鉄による買収提案の再審査を指示したことを歓迎する声明を発表し、「今日の大統領の決定は、アメリカ鉄鋼業への投資を実現する上でとても重要だ」と述べています(日テレNEWS)・・>>
ブルームバーグなどによると、このニュースのあとにUSスチールの株価はサーキットブレーカーが発動されて一時取引停止になるほど、急騰しました。機能の終値は16%以上高くなった(44.50ドル)ものの、日本製鉄による買収提案額(55ドル)をまだまだ大きく下回っている、とも。
<<・・石破茂日本首相がドナルド・トランプ米大統領と7日(現地時間)関税問題で25分間通話した。石破首相は通話の後、「日本が5年連続米国の最大投資国であり、関税政策が日本企業の投資能力を減少させる可能性がある」と伝えた。日米貿易交渉の米国側代表者に指名されたスコット・ベセント米財務長官は、日本が迅速に交渉に乗り出した対価で「優先交渉の対象になるだろう」と見通した。現在、日本は赤堀毅 外務省外務審議官と松尾剛彦 日本経済産業省経済産業審議官など次官級人事を米国に派遣した状態だ・・
・・日本側は9日に発動される相互関税だけでなく、鉄鋼・アルミニウム、自動車など関税賦課局から日本を除外してほしいと要求している日本経済新聞は、米国側が農産物関税を問題としているが、本格的な交渉のための条件をまだ明確ではないと述べた。一方、トランプ大統領はこの日、米国国家安全保障委員会に日本製鉄のUSスチール買収提案を再び見てほしいと述べた(ソウル経済)・・>>
ここからはいつもの告知ですが、新刊のご紹介です。本当にありがとうございます。<THE NEW KOREA(ザ・ニューコリア)>という1926年の本で、当時の朝鮮半島の経済・社会発展を米国の行政学者が客観的に記録した本です。著者アレン・アイルランドは、国の発展を語るには「正しいかどうか」ではなく、ただ冷静に、データからアプローチすべきだと主張し、この本を残しました。どんな記録なのか、「正しい」が乱立している今を生きる私たちに、新しい示唆するものはないのか。自分なりの注釈とともに、頑張って訳しました。リンクなどは以下のお知らせにございます。
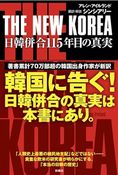
 ・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年3月2日)<THE NEW KOREA>です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。 ・準新刊は、<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。 ・既刊として、<Z世代の闇>も発売中です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。 ・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。
・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年3月2日)<THE NEW KOREA>です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。 ・準新刊は、<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。 ・既刊として、<Z世代の闇>も発売中です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。 ・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。