さて、赤沢亮正経済再生担当大臣が訪米し、米国側と2回目の関税交渉を行いました。まだ今朝の時点では具体的な話は出ていませんが、経済安保関連についての議論はあったけど、安保(防衛費)関連は議題にならなかったとのことです。前は防衛費関連の話もあったという報道があったので、これは「とりあえずは」よかったと言えるでしょう。また、為替レート関連も議題にはならなかった、とも。前回の交渉、そしてG20財務省会議で加藤勝信財務大臣が米国側と話したあとに、一部メディアが「為替レートについても話があった」と報じていて、加藤財務相が「そんなことはなかった」と話したりしましたが、やはりこの件も関税交渉とは別になるのでしょうか。というか、金利を引き上げている国に通貨安のことを話しても意味ないでしょうに。
今回の交渉内容だけでなく、韓国メディアの関連ニュースはいつも「えっ、そっち?」なものが目立ちます。関税関連で石破総理とトランプ大統領が電話会談したときには「石破総理があせって夜遅く会談した」という趣旨の報道が多かったですが、電話会談だとそうめずらしいことでもないし、そのあとにハンドクス権限代行とトランプ大統領も夜遅く電話会談しました。トランプ大統領が急に関税交渉に参加したときには、「トランプに完全やられた」「主導権はトランプに」などと報じていましたが、その翌日には複数のメディアが「韓国との交渉にもトランプ大統領が参加するなら、大きなチャンス」と報じていました。昨日は、「日本はトランプを信じていたのに、成長率展望が半分になった」という記事もありました。トランプ関税が影響したのは確かにあるでしょうけど、成長率関連だと韓国でも多くの記事が出ていたので、記事の題を見てちょっと笑ってしまいました。
そんなところ、ですが・・「言葉をすぐに変えるトランプ大統領に対し、日本は落ち着いた対応をしている」という記事もあります(韓国日報、1日)。これがどういう意味なのかと言いますと、ちょうど今日、ハンドクス総理が出馬宣言をしましたが、「関税交渉を急いで進めて、大統領選挙前になにかの結論を出そうとしているのではないか(それで支持率を上げようとしている)」という見方が出ています。新聞に載る1コマの漫画(政治家を風刺するイラスト)で、どの新聞だったかは覚えていませんが、ハンドクス総理とトランプ大統領がカードゲームをしている絵でした。ただ、ハンドクス総理はカードを「トランプから見えるように(カードの裏面が自分に向くように)」持っていました。そんな中、「急がない」、焦っているのは米国の方ではないのか、そんなスタンスの日本に対し、これまたベンチマークしようという意味もあったのでしょう。以下、<<~>>で引用してみます。
<<・・米国との二次関税交渉を控えた日本が(※交渉直前の記事です)「ゆっくり戦略」を駆使すると見られる。ドナルド・トランプ米大統領が相次いで関税措置を変えながら、焦っている側面を見せているという判断からだ。時間をかけて米国側の意図を正確に把握した後、交渉カードを準備するものと見られる。1日、朝日新聞、毎日新聞などによると、フィリピンを訪問中の石破茂首相は前日、現地で記者たちと会い、「まだ米国側の具体的な要求が確認できず、赤沢経済再生担当大臣に「米国側の意見を聞いて」と指示した。
関税交渉担当長官の赤沢大臣は、米国との二次関税交渉を控えて、前日の午後、米国に出国し、1日午後(現地時間)ワシントンでスコット・ベッセント米財務省長官、ジェミソン・グリア貿易代表部(USTR)代表と会う予定だ。先月16日、1次交渉の際にサプライズ登場したトランプ大統領は、今回の交渉には出ないことが分かった・・・・日本は、今回の二次交渉でも、本格的な接点の絞り込むために乗り出すのではなく、それよりは米国側の立場を聞くことだけに集中することが分かった。朝日新聞は「(非関税障壁)緩和策と、(農産物)輸入拡大の可能性を示して、米国側の出方を見守るものと思われる」とし「二次会談で交渉がどれほど進展するのかは分からない状況」と述べた・・
・・日本側が余裕を見せているのは、「時間は私たちの味方」という判断による。米国は3日から自動車部品に25%の追加関税をかける予定だった。しかし商務省は関税施行をわずか4日残した先月29日、自動車部品関税の緩和を発表した。カナダ・メキシコ産輸入品に対する25%関税施行を1日前に控えた時点でも猶予を発表した・・・・トランプ大統領がまた、言葉を急に変えることができるだけに、交渉カードは可能ならゆっくり出していくというのが日本側の戦略だ。日本政府のハイレベル関係者は朝日新聞に、「無理な関税措置で、米国が自滅することだってある」とし、「下手に複数のカードを提示したところで、取られるだけだ。急ぐ必要はない」と話した(韓国日報)・・>>
ここからはいつもの告知ですが、新刊のご紹介です。本当にありがとうございます。<THE NEW KOREA(ザ・ニューコリア)>という1926年の本で、当時の朝鮮半島の経済・社会発展を米国の行政学者が客観的に記録した本です。著者アレン・アイルランドは、国の発展を語るには「正しいかどうか」ではなく、ただ冷静に、データからアプローチすべきだと主張し、この本を残しました。どんな記録なのか、「正しい」が乱立している今を生きる私たちに、新しい示唆するものはないのか。自分なりの注釈とともに、頑張って訳しました。リンクなどは以下のお知らせにございます。
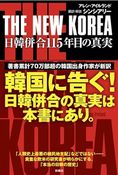
 ・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年3月2日)<THE NEW KOREA>です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。 ・準新刊は、<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。 ・既刊として、<Z世代の闇>も発売中です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。 ・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。
・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年3月2日)<THE NEW KOREA>です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。 ・準新刊は、<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。 ・既刊として、<Z世代の闇>も発売中です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。 ・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。