米国のハワードラトニック商務長官に、FOXニュースが「韓国は交渉(米国との関税関連交渉)が進行中なのか、彼らは日本を羨ましがっているのか」と質問しました(29日付「聯合ニュース」からの直訳)。そういうイメージとして見られているのでしょうか。長官は、韓国代表団が(トランプ大統領と一緒にラトニック長官が訪問中の)スコットランドまで来たことを明らかにして、「彼らがどれだけ交渉を望んでいるのかを考えてみてほしい、という話だ」と話しました。ハンギョレ新聞日本語版(26日)によると、現地時間で24日、ラトニック長官はCNBCとのインタビューでも、EUと韓国が交渉に積極的に乗り出しているとしながら(まだEUと米国の関税交渉が妥結する前です)、「韓国は日米合意を見て、『そんな、まさか』と思っただろう」と話したことがあります。
<<・・日本が5500億ドル(約80兆円)の投資の見返りとして関税引き下げを得たことが他の国々との交渉の構図を変えたと強調した。ラトニック長官は「韓国と日本は互いを常に意識している。韓国が(米国と)日本との合意内容を読んだら、悔しがる声が聞こえてくることだろう」として、このように述べた。「日本が合意したことを見た時、韓国が何を思ったか、想像に難くない。おそらく『そんなまさか』という反応だっただろう」とし、「今日韓国は私のオフィスに来て対話を交わす予定だ」と述べた(ハンギョレ新聞、26日)・・>>
フォックスニュースの質問も、このような発言によるものでしょう。相次ぐ関連交渉のキャンセルで、結局、期限前日の31日に2+2(外務、通商)会談を開くことにした韓国と米国。聞くところ、農産物市場の開放もほぼ決まっているような流れで、特にお米の場合、「米の市場開放も難しい」「日本とは異なり、韓国は2019年の関税率交渉の結果に応じて、国別に低率関税割当制を通じて輸入する輸入米の規模を定めたため、米国産の輸入量を増やせば、他の国々の分を再調整しないといけない」(京郷新聞24日)とのことでしたが、どうやら流れが変わったようです。なにより、28日~29日には、米中関税交渉が行われます。関税猶予期間の延長について話し合う、と言われています。これが上手く行かなかった場合、31日にちゃんと会談ができるのか、そんなところも気になります。
そんな中、米国を訪問予定の(31日の関税交渉のため)韓国の趙顕 外交部長官(外相)が、先に日本を訪れることになりました。朝鮮日報(28日)は、関税交渉の助言を得るためでもある、と報じています。韓国の外交部長官は、普通、米国から訪問します。米国以外の国を最初に訪問するのはかなりの異例である、とも。以下、<<~>>で引用してみます。
<<・・趙顕 外交部長官が29日、就任以来初めて日本を訪問し、岩屋毅日本外相と韓日外交長官会談を行う。来る31日ワシントンDCで韓米外交長官会談をする前に、まず日本を訪れるのだ。長官は、日本が最近米国と関税交渉を妥結しただけに、日本に関連のアドバイスも求めることが分かった。政府情報筋によると、趙長官は29日訪日して、当日、韓日外交長官会談を行い、翌日に東京からアメリカワシントンに向かって31日(現地時刻)マルコ・ルビオ米国務長官と会う予定だ。関税交渉時限(8月1日)前日に初の韓米外交長官会談が開かれるのだ。長官は今回の韓日会談で、韓日、韓米日協力の重要性を再確認し・・
・・韓国と経済・安保の面で同様の処遇にある日本が、22日、先に米国と通常交渉を妥結した。これに関して両側間の意見交換もあると思われる。外国メディアの報道によると、欧州連合(EU)も27日、米国と交渉を妥結する前に、日本の関税交渉関係者たちと会って米国への対応法など各種の助言を求めたという。韓国外交部長官が就任初の海外出張で米国以外の国を先に訪れるのは異例だ。長官は最近就任以後、海外出張地を決める際に、無条件に前例に従うのではなく、「戦略的柔軟性」を持って実理的に検討することを幹部たちに注文したという。彼は先に長官候補だった時も「就任すれば米国から行かなければならないという固定観念から抜け出さなければならない」と話したことがある(朝鮮日報)・・>>
最後の部分、それは「中国に行くこともできる」と話しただけでしょうに。ちなみにこの趙顕外交部長官、本ブログで前にも取り上げたことがありますが、次官だった頃(2019年)、日米韓関係において、「米国が日韓関係を懸念しているのは、日本が米国に間違った情報を伝えているからだ」と主張していました(2019年2月15日聯合ニュース)。せっかくだからもう一度、どうぞ。 <<・・趙顕外交部1次官は15日「日本が非常に多様に、自分たちの立場を歪曲して話すことが感知される。そこに積極的に、うまく対応していかなければならないと思われる」と明らかにした・・・・「(訪米した際、米国側が)日韓関係を心配していると、私たちに強調する感じを受けた」と話す李海瓚(※当時)共に民主党代表の発言に対し、「私たちは、深く悩んでいるところだ」としながら、このように述べた(聯合ニュース2019年2月15日)・・>>
今日の更新はこれだけになります。次の更新は、明日(30日)11時頃になります。
ここからはいつもの告知ですが、新刊のご紹介です。本当にありがとうございます。<THE NEW KOREA(ザ・ニューコリア)>という1926年の本で、当時の朝鮮半島の経済・社会発展を米国の行政学者が客観的に記録した本です。著者アレン・アイルランドは、国の発展を語るには「正しいかどうか」ではなく、ただ冷静に、データからアプローチすべきだと主張し、この本を残しました。どんな記録なのか、「正しい」が乱立している今を生きる私たちに、新しい示唆するものはないのか。自分なりの注釈とともに、頑張って訳しました。リンクなどは以下のお知らせにございます。
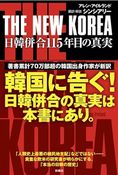
 ・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年3月2日)<THE NEW KOREA>です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。 ・準新刊は、<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。 ・既刊として、<Z世代の闇>も発売中です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。 ・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。
・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年3月2日)<THE NEW KOREA>です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。 ・準新刊は、<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。 ・既刊として、<Z世代の闇>も発売中です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。 ・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。