日本の大学で教授を務めている韓国人専門家(国際政治経済学)が、今回の日米、米韓関税交渉について分析した記事があったので、取り上げてみます。毎日経済(毎経エコノミー)、3日の記事です。記事は別に勝ち負けにこだわった内容ではありませんが、ただ、日本側がずっと有利だという結論になっています。たとえば、「それぞれの国の国内法で解決できる内容なのかどうか」という観点から、日本のほうがまともな内容だという結論になっています。国内法という観点からの分析が、他の分析記事よりユニークですが、韓国側に「日本のほうが良かったという記事」が載ったのもあまりにも異例です(笑)。日米の関税関連投資が「トランプ大統領の任期内」で、韓国の場合は「10年間200ドルずつ」というのも、韓国側の記事では初めて読んだ気がします。
また、交渉(合意)内容そのものもそうですが、もしその履行に問題があった場合、日本の場合は国内法を限界を超えない範囲で解決できるようになっているけど、韓国の場合はそうではなく、実際、大統領室などから「米韓関税合意を履行するには、国内法の改正(特別法の制定)が必要だ」と公言しています。記事は、「途上国が援助を受けるときに国内法を改正することがあるが、特別法まで作るのは見たことがない」としています。どうやら、韓国の場合は「そもそも、国内法を改正(特別法の制定)を前提にして」の交渉だった、とのことでして。以下、<<~>>で引用してみます。
<<・・赤沢亮正、日米関税交渉団代表は、経済産業相に任命された。自民党総裁候補だった時、5人の総裁候補の中で唯一再交渉の可能性に言及した高市早苗首相は、なぜ彼を経済産業省の首長に任命したのだろうか。日米間の了解覚書で最も注目すべき点は、その「第21条」、両国相互間の国内法を尊重し、各国は国内法を超えた義務を持たないという条項だ。一見、平凡に見えるが、「第7条」と合わせてみると、その効力が明確になる。第7条は、米国が、日本の審査を受けるため投資案を随時提供するということから始まる。そして、「ドルで表示された、すぐに使用可能な資金」を、日本が指定口座に入金し、日本が定められた期限内に入金しなかった場合、米国が関税を高めることもできるという内容が続く。
第21条を念頭に置いて第7条を解釈してみると、米国が投資先を特定して投資案を提供すれば、日本は国内法と関連手続により、投資適格性等を審査する権限を有する。また、日本国内法上、国民の税金に基づく資金を、任意に現金出資形態で海外送金できる公的機関は存在しない。当たり前だが現金出資は制限され、ほとんどは、既存の金融公社がしてきたローンや支払保証の形で定められた手続きを経て、それから米国に提供されるしかない。第21条は、現金出資要求を実効的に遮断しているわけだ。さらに、日本が定められた期限内に入金しなかった場合、米国が関税を高めることができるという条項も、もっと考えてみる必要がある。
これは、日本が審査した後に、国内法を理由にその投資に応じないこともまた、日米の了解覚書に違反しない、「一つの選択肢」であることを明示しているのだ。むしろ、トランプ大統領が指定した投資案に、日本は国内法により応じないこともできるので、投資委員会の段階から慎重に日本国内法と手続きを考慮すべきだという、厳重な警告になる。
他にも、日米の了解覚書で資金提供期限をトランプ大統領の「今回の任期」に限定した点も目立つ。日本は、国内法と手続きを遵守して投資先を推薦して投資するものの、2028年末からは投資義務が消える。特に来年2月、米最高裁判所の判決前までは、米国も多くの投資プロジェクトを繰り広げることは難しいという点まで勘案すれば、時間はあまり残されていない。結局、エネルギー、AIなどの両国の理解が一致する分野に、無難に日本側の審査をクリアー出来ると予想される分野に、投資が集中し、加速することになるわけだ。米国は、日本が乗り気でない分野については、(※日本からの投資資金ではなく)他の投資財源を模索するだろう。
10月29日、関税交渉の後、金容範政策室長は、「私たちはMOUを履行するために法が改正されなければならず、その法が国会に行って通過しなければならないという条項もある」と明らかにした。日米間の「相互国内法を尊重する」という条項が、米韓の間では「韓国の法を改正する」という前提条件になっている。新たに新設される「対米投資ファンド新設特別法」により、国内金融公社が申請及び内部審査手続きもせず、投資先が特定されていない米国基金に毎年現金200億ドルずつを10年間納入することになるのではないか、そこが懸念される。トランプ大統領の任期後、米国が関税撤廃の雰囲気に回帰しても、引き続き納入しなければならないのではないか、そこも疑問だ。
途上国が援助を受ける時、しばしば国内法改正が前提となる。しかし、特別法まで作って税金に基づく現金を納入するという交渉は、あまり見たことがない。国民に莫大な負担をもたらす。これからも、政府であれ民間であれ、様々な「甲(※上の存在)」たちとの交渉は数えきれないほど多いだろう。「静かな一手」で実利を守り、その功労者が重用されるシステムを備える必要がある(毎経エコノミー)・・>> 今日の更新はこれだけです。次の更新は、明日(5日)の11時頃になります。
ここからはいつもの告知ですが、新刊のご紹介です。いつも、ありがとうございます。今回は、<韓国リベラルの暴走>という、李在明政権関連の本です。新政権での日韓関係について、私が思っていること、彼がいつもつけている国旗バッジの意味、韓国にとっての左派という存在、などなどを、自分自身に率直に書きました。リンクなどは以下のお知らせにございます。

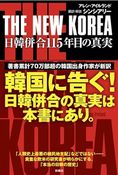 ・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年8月30日)<韓国リベラルの暴走>です。韓国新政権のこと、日韓関係のこと、韓国において左派という存在について、などなどに関する本です。・準新刊は<THE NEW KOREA>(2025年3月2日)です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。・既刊、<自民党と韓国>なども発売中です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。
・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年8月30日)<韓国リベラルの暴走>です。韓国新政権のこと、日韓関係のこと、韓国において左派という存在について、などなどに関する本です。・準新刊は<THE NEW KOREA>(2025年3月2日)です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。・既刊、<自民党と韓国>なども発売中です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。