来年1月13日、韓国銀行(中央銀行)金融通貨委員会がもう一度基準金利を引き上げる可能性が高い、と報じられています。物価上昇率もまだまだ5%台で、いつものこと、米国との金利差が広がっているからです。さすがに今回も0.25%p引き上げになるのではないかという予測が主流ですが、すでに何度も利上げしているので、それだけでも影響は結構大きいだろう、とも。一部のメディアが、「金利引き上げの速度調整が必要だ」という主張を出していますが、昨日は、右側とされる中央日報からも同じ記事がありました。
右側のメディアでこのような主張を見るのは、珍しい気もしますが・・記事の内容は、迂回的な表現ではありますが、結局は金利引き上げが「サブプライムローン」の重要な要因であり、「韓国版サブプライムローン」の影にもっと注意を払うべきだ、としています。中央日報の記事は、「不動産市場が『滑り台』状態にある」としながら、まだまだ底は見えず、不動産価格下落の主な要因である金利がどこまで上がるのか、いつまで続くのかも分からない状態だとしながら、このように報じています。以下、<<~>>が引用部分となります。
<<・・2007年米国のサブプライムローン事態の「ひきがね」の役割をしたのも、金利だった。米国の中央銀行に当たる米連邦準備制度理事会(FRB)は、年1%まで下がっていた政策金利を5.25%まで引き上げた。高騰する物価がその理由だった。超・低金利で隠されていた住宅ローンの問題が表面化し、金融市場まで波及した。まともな職業も所得もない人たちにお金を貸して(サブプライム・ローン)家を買うようにうながしたのが、問題の根本だった。
現在の状況は、当時とそっくりだ。物価上昇→金利引き上げ→不動産価格下落。静かに、段階を登っていくとことである。違う点もある。家計債務状況だ。中央銀行の金融安定報告書によると、2007年7~9月期に名目国内総生産(GDP)比で68.2%だった家計信用(※家計債務全般)比率は、今年7~9月期には105.2%まで上昇した。1年間、国全体が稼いだ金額をすべて注ぎ込んでも、家計の債務を完全に返済することはできないという意味だ。
そのような中、政府は住宅担保認定比率(LTV)、総債務償還比率(DTI)、総債務元利金返済比率(DSR)などでローンを制限しているから、銀行がドミノ式に倒れる「システム・リスク」の可能性は小さいと、繰り返し強調している。「あらゆる手段を講じて、あなたの家の価格が半減しても、あなたのジョン背(伝貰)保証金が消えても、銀行は上がった金利に合わせてきっちりとローンの利子と元金を回収するから、何の問題もありません」。そう言っているのと同じだ(中央日報)・・>>
家計債務がGDPを超えているのはたしかに印象的ですが、個人的に、それを言うなら可処分所得のほうでしょう、と思っています。家計債務を処分可能所得比で考えてみると、2008年には138.5%でしたが、2020年には200.7%まで増えました。確か、140%超えたときから、アメリカのサブプライム住宅ローン事態の「可処分所得対比家計債務」よりもっと高くなったという記事が結構出ていました。それが、いつのまにか200%を超えたわけです。
あと、サブプライムというのは、いわゆる『弱い環』のことです。個人的な意見ですが、金融機関も同じく『弱い環』を考えるべきではないでしょうか。第3金融圏(貸付業者)はともかくして、第2金融圏のことです。もっとも気になるのは、プロジェクト・ファイナンス(PF)です。本ブログでも何度か取り上げましたが、たとえばマンション団地を作るとした場合、それが成功する、殆ど売れるという前提で、工事の前から金融機関からローンを受け、作ってもいない物件の販売を始めます。こちらも中央日報(10月25日)の記事ですが、2008年には、第1金融圏、すなわち普通の銀行が主にやっていました。しかし、いまは違います。
<<・・PFが問題になったのは、2008年の金融危機以降だ。それまでPFは、ほとんどが銀行(※普通の銀行、第一金融圏)で取り扱っていた。銀行は自己資本に余力があり、PF進行中に問題が生じても、銀行レベルでなんとか対応できた。また、当時は、PFの基本前提が「建設会社(施工会社)の支払い保証」だった。該当事業の進行に支障が生じても、建設会社が代わりに返済するという約束が必要だった・・
・・(※2008年以降)大きくなったリスク負担で、銀行が慎重になっている間に、保険会社、証券会社、与信会社、貯蓄銀行、キャピタル(※第2金融圏)などが入ってきた。保険会社の場合、2012年に13%水準だった保険会社のPF貸付の割合は、去年6月基準でで38%に急増した。同じ期間、与信会社が占める割合も7.4%から23.7%に上昇した。自己資本に余裕がない中小証券会社は、特にPFに頼っている。信用評価機関によると、証券会社24社の自己資本に対するPF(ブリッジローン+本PF)の割合は、平均39%だ・・>>
2008年以降、第1金融圏(普通の銀行)は、プロジェクトファイナンスから距離を置くようになり、その隙間に、第2金融圏が、まさにヨンクルのように投資を行うようになった、と。すなわち、買った人たちだけが「サブプライム」なわけではありません。関わっている金融機関もまた、金融機関としてはサブプライムなわけです。
本エントリーにコメントをされる方、またはコメントを読まれる方は、こちらのコメントページをご利用ください。以下、拙著のご紹介において『本の題の部分』はアマゾン・アソシエイトですので、ご注意ください。

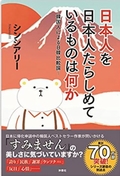 ・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2022年9月2日)からですが、<尹錫悦大統領の仮面 (扶桑社新書)>です。文在寅政権の任期末と尹錫悦政権の政策を並べ、対日、対米、対中、対北においてどんな政策を取っているのかを考察しました。政権交代、保守政権などの言葉が、結局は仮面が変わっただけだということ、率直に書きました。 ・準新刊<日本人を日本人たらしめているものはなにか~韓国人による日韓比較論~>も発売中です。「私はただ、日本が好きだから、日本人として生きたいと思っています」。これが、本書の全て、帰化の手続きを進めている私の全てです。 ・既刊として、日本滞在4年目の記録、<「自由な国」日本「不自由な国」韓国 韓国人による日韓比較論 (扶桑社新書) >と、新しく出現した対日観について考察した<卑日(扶桑社新書)>も発売中です。 ・新刊・準新刊の詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。 ・本当に、本当にありがとうございます。書きたいことが書けて、私は幸せ者です。それでは、またお会いできますように。最後の行まで読んでくださってありがとうございます。
・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2022年9月2日)からですが、<尹錫悦大統領の仮面 (扶桑社新書)>です。文在寅政権の任期末と尹錫悦政権の政策を並べ、対日、対米、対中、対北においてどんな政策を取っているのかを考察しました。政権交代、保守政権などの言葉が、結局は仮面が変わっただけだということ、率直に書きました。 ・準新刊<日本人を日本人たらしめているものはなにか~韓国人による日韓比較論~>も発売中です。「私はただ、日本が好きだから、日本人として生きたいと思っています」。これが、本書の全て、帰化の手続きを進めている私の全てです。 ・既刊として、日本滞在4年目の記録、<「自由な国」日本「不自由な国」韓国 韓国人による日韓比較論 (扶桑社新書) >と、新しく出現した対日観について考察した<卑日(扶桑社新書)>も発売中です。 ・新刊・準新刊の詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。 ・本当に、本当にありがとうございます。書きたいことが書けて、私は幸せ者です。それでは、またお会いできますように。最後の行まで読んでくださってありがとうございます。