務安国際空港で起きた済州(チェジュ)航空機事故のことで、多くのメディアがバードストライクを原因としています。しかし、一部のメディアは海外専門家たちの見解を引用しながら、バードストライクであれほどの事故が起きることはそうないとしながら、別の原因を指摘しています。コンクリート入りの外壁関連記事も多いですが、そもそも機体が胴体着陸した原因としては、やはり整備問題が注目されています。LCC、低価格航空社同士の価格競争などが原因で、整備時間が短すぎるという問題が前から指摘されていました。
中には、匿名投稿ではあるものの、実際に整備を担当していた人たちからの指摘もありました。もちろん、LCCだからといって、ちゃんとした整備が確保できている所も多いでしょうし、それが普通でしょう。しかし、韓国日報(1月5日)の記事は、いま価格競争がやりすぎだと指摘しています。韓国の低価格航空社は「海外航空券を3万ウォン(約3300円)で販売している」という題です。この状況で果たして整備のための人、時間が確保できるのか、という趣旨です。以下、<<~>>で引用してみます。
<<・・済州航空だけでなく、全体的なLCCが低価格競争の中で整備費用を減らそうと、安全をおろそかにしているのではないかという懸念が広がっている。国内LCC業界20年、最大のピンチになるという見通しも出ている。1990年代、米国とヨーロッパを中心に始まったLCC市場は、世界的な海外旅行需要の増加と相まって、急速に成長した。 LCCは、高い航空機稼働率、地上待機時間の最小化、機内サービス有料化などのコスト削減戦略を通じて、驚くほどの低価格を提示して、成功を収めた。しかし、その一方で、乗客の安全関連費用を削減し、整備部門を外注化するなど、重大なリスクをもたらした・・
・・韓国は、国土の大きさに比べて、世界的に見ても多くのLCCを保有している(※日本の場合は4社だそうです)。業界1位の済州航空をはじめ、ジン・エア、エア釜山、イースター航空、エア・ソウル、ティーウェイ航空、エア・プレミアなど7つに達する。韓国の面積の98倍に達する米国と同じくらいの水準だ。市場は小さいので、競争が強くなり、整備への投資が弱くなってきたのだ・・
・・8年間、国内LCCの中で国土交通部が提示した整備人力勧告基準である「航空機1台当たり12人」を満たしたのはわずか2社(済州航空・イースター航空)にすぎなかった。済州航空は12人をやっと越えていた。ジンエア、エア釜山などは10人にも及ばなかった。人員があまりにも足りないだけでなく、力量も問題だという指摘も出ている。 LCC整備士たちは、エンジン修理が必要となるほど大きな問題が疑われた場合、その10件のうち7件(71.1%)以上において、自分たちでの整備を放棄し、航空機を海外に送り修理を受けることが分かった。新型コロナ当時、ベテランの整備要員の多くが業界を離れ、整備要員の不足とメンテナンスレベルの低下の問題がさらに進行していった。このような状況のため、飛行中に問題が起きて回航して戻ってくる場合が続出している・・
・・航空安全専門家はこれを「整備をおろそかにするのが慢性化された結果が」と見る。ファン・ホウォン韓国航空隊航空宇宙政策大学院長は、「整備士3~4人がしなければならないことを1~2人が支えている状況だ」とし「会社の立場では、3人を雇うよりも2人だけ雇用して、勤務時間を超えて働かせ、相応の手当を払ったほうが、費用面でより有利になる。だから、人をもっと雇おうとはしないのかもしれない」と話した。続いてファン院長は「整備士の数字と同じくらい重要なのが、整備に使われる時間だが、低価格航空会社は旅客機の稼働時間を最大値に引き上げるために、整備時間を最小限にする」とし、「小さな問題なら、それを問題にしないでそのまま進めるよう、整備士を圧迫することだってある」と指摘した。整備が長くなって、飛行機が離陸できなくなることがあったら、その後の飛行スケジュールに問題が生じ、損失が大きくなるためだ。
実際、昨年ティーウェイ航空は機体問題を理由に離陸に応じなかった機長に「停職5ヶ月」という重い措置を下した。昨年1月12年機長A氏は、ベトナムカムライン空港から仁川空港へ向かう飛行機の離陸を準備していたところ、ブレーキパッドの摩耗状態を知らせる部品の長さが基準値に満たなかったことを発見して、ブレーキ交換を要請したが、整備を受けることができなかった。整備を終えていない状態で離陸できないと判断した機長は、運航に応じなかったが、これに対して航空会社側は「飛行安全が十分に確保されたにも運航に応じなかったこと」という理由で停職5カ月を下した(韓国日報)・・>>
ここからはいつもの告知ですが、久しぶりに新刊のご紹介です。本当にありがとうございます。新刊は自民党と韓国」という題です。岸田政権・尹政権になってから、「関係改善」という言葉がすべての議論の前提になりました。果たして、本当にそうなのでしょうか。いや、それでいいのでしょうか。じゃ、同じ路線でないのは、たとえばこれから日本政府の路線変更があった場合は、それは「改善」ではないのでしょうか。そんな疑問に対する考えを、自分なりに、自分に率直に書いてみました。リンクなどは以下のお知らせにございます。
本エントリーにコメントをされる方、またはコメントを読まれる方は、こちらのコメントページをご利用ください。以下、拙著のご紹介において『本の題の部分』はアマゾン・アソシエイトですので、ご注意ください。

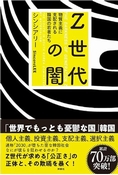 ・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2024年12月22日)<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。・準新刊(2024年5月2日)は、<Z世代の闇>です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。・既刊として、<韓国の絶望、日本の希望(扶桑社新書)>も発売中(2023年12月21日)です。「私たち」と「それ以外」、様々な形で出来上がった社会の壁に関する話で、特に合計出生率関連の話が多目になっています。・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。
・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2024年12月22日)<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。・準新刊(2024年5月2日)は、<Z世代の闇>です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。・既刊として、<韓国の絶望、日本の希望(扶桑社新書)>も発売中(2023年12月21日)です。「私たち」と「それ以外」、様々な形で出来上がった社会の壁に関する話で、特に合計出生率関連の話が多目になっています。・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。