以下、PF(プロジェクトファイナンス)関連の話が出てきます。いままで本ブログ及び星の数ほど多い記事群がプロジェクトファイナンスのことで うわあぁな内容を報じてきましたが、珍しく、本ソース記事(ソウル経済2月5日)でいうPFは、海外で行われているきれいなPF(?)のことです。これ、多くの他の案件もそうですが、韓国不動産市場でマンション団地建設などのために行われるPFの場合、他国に比べて、すごぉく、ユニークな制度です。いくらなんでも自己資本が少なすぎること、融資と信用のバランスが合ってないこと、民間マンション団地だけに集中していること、などです。
海外の場合は、もちろん民間で行われることもありますが、主に政府や自治体の保証または支援が得られる社会基盤施設、社会間接資本投資などで主に行われています。ザファクトというネットメディアの記事(2022年12月2日)によると、「(根本的な解決策として)金融圏が、お金を確実に返せそうなところに融資すれば問題ないだろう。実際、海外ではPFというものが、主に社会資本(SOC、Social Overhead Capital)を工事する際に発生する。国内ではそうではない。建設会社が信用度や担保などを提供して融資を受ける場合が多い」としています。ケース・バイ・ケースでしょうけど、海外と国内でかなり状況が異なるというのは、他のサイトも同じ記述をしています。
すなわちここでいう「海外PF」というのは、ある意味ではいままで書いてきた国内PFとは逆の意味で、信頼できる大規模工事、特に海外の社会間接資本関連の工事のことです。ソース記事の趣旨的に。で、その記事で主に書いている内容は何なのかと言いますと、韓国の場合、三菱UFJ銀行など日本の銀行が主管しないと、PFなど海外の大規模工事に参加することも難しい、とのことでして。理由は簡単で、国内にはそういう方面で影響力を持つ銀行が無いからです。様々な形で、前から指摘されてきた、「経済規模に比べて金融が弱い」という話。その一つになるでしょう。ちなみに、三菱UFJは、この方面ではディール規模でグローバル1位だそうです。また、2位は三井住友銀行、3位はみずほ銀行で、日本の銀行の影響力が強い、とも。以下、<<~>>で引用してみます。
<<・・「グローバル1位は三菱UFJ、日本の銀行がないと海外PFできない」(※題)。 国内の各銀行が、大規模な海外の建設事業や発電所建設などに必要なプロジェクト・ファイナンシング(PF)主管作業に参加できないでいることが分かった。銀行の規模が小さいため貸付金利が高く、その限度額も限られるからだ。しかし、国内の各銀行が、国内で容易な利息が得られる商売だけに集中し過ぎで、海外進出の経験そのものが少ないため、海外PFに参加できない現象がさらに強くなりつつあるという指摘も出ている。5日、金融界によると、グローバル金融市場で最高PF事業者と評価される大型銀行は、JPモーガンチェイス、シティグループ、バンクオブアメリカ(BofA)、ウェルズファーゴ、ゴールドマンサックスなどだ。欧州系銀行もあるが、BNPパリバやソシエテジェネラル・クレディアグリコルなどが代表的だ。特に、日本の銀行がPFで強さを発揮している。ミズホファイナンシャルグループと三菱UFJファイナンシャルの場合、全世界金融市場でも指折りのPF強者だ。
「IJグローバル」によると、2023年上半期グローバルファイナンシング主線事業者(MLA)ディール規模1位は、日本の三菱UFJで95億9700万ドル(約13兆8600億ウォン)規模のプロジェクトを遂行したと集計された。2位も日本の大手金融会社である三井住友(SMBC)だった。 SMBCのPF周旋規模は77億9300万ドルだ。3位も日本系のみずほ(70億600万ドル)で、1~3位がすべて日本の銀行だった。一方、韓国の金融会社は20位まで一社も確認できなかった。韓国が位置するアジア太平洋(APAC)地域でも日本が強勢を見せた。1位はSMBCで24億3300万ドルのディールを周旋し、2位(三菱UFJ、15億3700万ドル)と4位(みずほ、11億7500万ドル)が日本の銀行だった。3位は香港のHSBCで12億3300万ドルのディールを周旋した。アジア太平洋地域でも国内金融会社は20位以内に入ることができなかった。
金融界では、国内企業の海外進出や大規模事業の受注の際、日本の銀行のPF主管なしには、事業が事実上不可能だという話が流れている。日本の銀行の場合、低い金利と長い経験をもとに、PFに強みがあるうえ、大株団の募集もスムーズにできる。国内の各銀行は、日本や主要金融会社が主管するPFに参加する形になるのが現実だ。日本の各銀行は、しばらく「ゼロ金利」に支えられ、大規模な資金を動員してPFに力を入れてきた。金融界のある関係者は、「国内の銀行の場合、基本的に海外銀行に比べて小さく、ドルなどの資金を調達できる金利も高く、相対的に競争力が弱いのが事実」としながらも「国内でばかり事業してきた影響があるのも認めざるを得ない」と指摘した(ソウル経済)・・>>
ここからはいつもの告知ですが、久しぶりに新刊のご紹介です。本当にありがとうございます。新刊は自民党と韓国」という題です。岸田政権・尹政権になってから、「関係改善」という言葉がすべての議論の前提になりました。果たして、本当にそうなのでしょうか。いや、それでいいのでしょうか。じゃ、同じ路線でないのは、たとえばこれから日本政府の路線変更があった場合は、それは「改善」ではないのでしょうか。そんな疑問に対する考えを、自分なりに、自分に率直に書いてみました。リンクなどは以下のお知らせにございます。
本エントリーにコメントをされる方、またはコメントを読まれる方は、こちらのコメントページをご利用ください。以下、拙著のご紹介において『本の題の部分』はアマゾン・アソシエイトですので、ご注意ください。

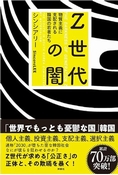 ・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2024年12月22日)<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。・準新刊(2024年5月2日)は、<Z世代の闇>です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。・既刊として、<韓国の絶望、日本の希望(扶桑社新書)>も発売中(2023年12月21日)です。「私たち」と「それ以外」、様々な形で出来上がった社会の壁に関する話で、特に合計出生率関連の話が多目になっています。・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。
・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2024年12月22日)<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。・準新刊(2024年5月2日)は、<Z世代の闇>です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。・既刊として、<韓国の絶望、日本の希望(扶桑社新書)>も発売中(2023年12月21日)です。「私たち」と「それ以外」、様々な形で出来上がった社会の壁に関する話で、特に合計出生率関連の話が多目になっています。・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。