何年か前から、だったと記憶していますが・・各メディアは中国の「専業子供」という言葉について報じるようになりました。他の国ではカンガルーという言葉を使う場合もありますが、就職せず、またはできず、親のもとで暮らす青年たちのことです。韓国の経済メディア「毎日経済」が、韓国でこれと同じ現象が現れていると報じました。そういえば去年、盧鋒 北京大学経済学科教授が「中国が巨大な韓国のように変わっている」と話し、韓国でも多くのメディアが取り上げたことがあります。大学進学率が高くなり、大卒者は増えたけど、そもそも働き口がないから就職できず、就職できるとしても、自分の目の高さに合った雇用を見つけることができず、『ただ休む』道を選択する青年が増えてきた、これは韓国そっくりだ、というのです。
似たような問題で、今回は韓国から「中国そっくりだ」という話が出てきたわけです。ちなみに、韓国でも「自分が納得できる就職先を探し、結局はなにもしなくなる」現象を、一部のメディアが「雇用ミスマッチ」と表現しています。確かに大卒者が多い(多すぎる)とかそういう側面があるし、雇用の質という側面の問題もあるので、アプローチの仕方としては別にいいと思いますが、韓国メディアの多くはこれらを雇用側の問題『だけ』にする論調が強く、個人的には違和感があります。どちらかというと、求職する側の問題(望みが高すぎる)のほうが、大きいのではないか・・私は、そう思っていますので。
さらに、求人倍率が0.28まで下がったというニュースが、多くのメディアから確認できます。仕事を望む100人がいて、実際の働き口は28人分しかない、という意味になります。2023年、当時、景気に関する記事が一気に増えましたが、当時も求人倍率が0.5以上はありました。国民日報によると、1999年1月、いわゆる「IMF期間」の頃、0.23まで下がったことがあります。人口減少とかあったとはいえ、いくらなんでもあのときと似たような数値が出たとは、驚きです。100人あたりの働き口が28個しかなく、6日にもお伝えしましたが非自発的失業者が137万人(日本35万人)なのに、公式失業率は去年~今年で2.8%~3.8%しか出ない(失業者111万5000人)から、もうなにがなんだかよくわかりません。以下、<<~>>で引用してみます。
<<・・「専業子供」という、最近の中国内の流行語は、青年たちの現実を反映している。専業子供は文字通り、職業なしで両親からお金をもらって生きることを意味する。青年失業が激しくなり、就職をあきらめてしまった専業子供が急増しているわけだ。韓国も中国に劣らず雇用が厳しくなっている。1月求職者1人当たりの雇用数を意味する求人倍率が0.28を記録した。「IMF期」直後の1999年1月以降、26年ぶりに最も低い、衝撃的な数値だ。中・長年が再就職競争を繰り広げ、青年たちは求職をあきらめる姿も、中国とよく似ている・・
・・安定した雇用を手にした一部の労働組合たちは、賃金削減もなく法定定年を65歳に上げるようにとの立場にこだわり、子供たちのハシゴをはずしている。定年延長は、大規模な労組がある大企業や公共機関など一部の労働者だけが恩恵を受ける仕組みだ。青年たちが好む雇用中心に定年が増えれば、青年たちは良質の労働市場に参入することが難しくなる。青年たちが生涯非正規職になるのではないかという展望まで出ている・・・・自ら作った硬直的労働市場で、短期的で不安定な雇用の中、子供たちは就職を諦めている(毎日経済)・・>>
<<・・求職者1人当たりの雇用数を意味する求人倍率が先月0.28まで下がった。国際通貨基金(IMF)の時期、199年以降、26年ぶりに最も低い水準だ。雇用保険常時加入者増加幅も2004年1月以来21年ぶりに最低値を記録した。建設・製造業を中心に景気鈍化が続き、企業の採用心理も萎縮したという分析が出ている。雇用労働部が10日公開した「2025年1月雇用行政統計で見た労働市場動向」によると、先月就職ポータル「ワークネット」に登録された新規求人人員は13万5000人だ。昨年1月と比べると40%を超える10万1000人(42.7%)が減った。先月、新規求職人員は47万9000人を記録した。
人口減少の影響で前年同月比3万3000人(6.5%)減少したが、求人人員減少の規模がはるかに大きかった。求人倍率は求人人員で求職人員を割った値で0.28を記録したが、これは1999年1月0.23以後、最も低い数値だ。求人倍率は2023年には、ほぼ0.6を超えていて、昨年は0.5前後まで上ったり下がったりしていた。そして去年12月に0.4まで下がった。雇用減少傾向がますます顕著になっているわけだ(国民日報)・・>>
ここからはいつもの告知ですが、新刊のご紹介です。本当にありがとうございます。自民党と韓国」という題です。岸田政権・尹政権になってから、「関係改善」という言葉がすべての議論の前提になりました。果たして、本当にそうなのでしょうか。いや、それでいいのでしょうか。じゃ、同じ路線でないのは、たとえばこれから日本政府の路線変更があった場合は、それは「改善」ではないのでしょうか。そんな疑問に対する考えを、自分なりに、自分に率直に書いてみました。リンクなどは以下のお知らせにございます。
本エントリーにコメントをされる方、またはコメントを読まれる方は、こちらのコメントページをご利用ください。以下、拙著のご紹介において『本の題の部分』はアマゾン・アソシエイトですので、ご注意ください。

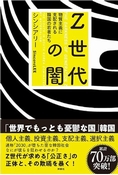 ・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2024年12月22日)<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。・準新刊(2024年5月2日)は、<Z世代の闇>です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。・既刊として、<韓国の絶望、日本の希望(扶桑社新書)>も発売中(2023年12月21日)です。「私たち」と「それ以外」、様々な形で出来上がった社会の壁に関する話で、特に合計出生率関連の話が多目になっています。・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。
・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2024年12月22日)<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。・準新刊(2024年5月2日)は、<Z世代の闇>です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。・既刊として、<韓国の絶望、日本の希望(扶桑社新書)>も発売中(2023年12月21日)です。「私たち」と「それ以外」、様々な形で出来上がった社会の壁に関する話で、特に合計出生率関連の話が多目になっています。・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。